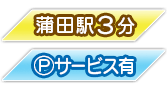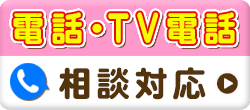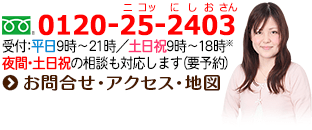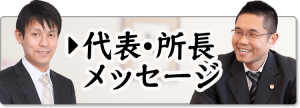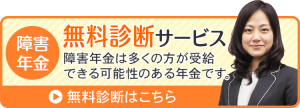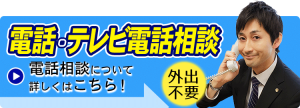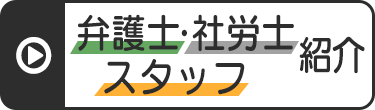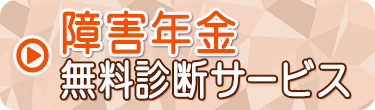自閉スペクトラム症で障害年金が受け取れる場合
1 自閉スペクトラム症で障害年金が受け取れる場合
初診日の時点において、国民年金または厚生年金に加入しており(年金制度に加入していない20歳未満の場合と、過去に年金制度に加入していた60歳以上65歳未満の場合も含む)、かつ年金保険料を一定程度納めており、自閉スペクトラム症によってコミュニケーション能力や社会性に問題があり、労働について著しい制限を受けたり、日常生活の適応にあたって援助が必要だったりする場合に、障害年金を受け取ることができます。
2 納付要件
障害年金を受給するためには、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上年金保険料を納めている、または免除等の手続きをとっているか、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納の期間がないことが必要になります。
ただし、初診日に20歳未満である場合には、公的年金の加入期間前なので、上記の納付要件は必要ありません。
なお、先天性の知的障害の場合は生年月日を初診日としますが、発達障害については年齢が高くなって初めて障害があることに気づくケースもあるため、実際に発達障害に関係する症状で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。
そのため、20歳になった後に受診した場合には、納付要件が問題なる可能性がある一方、仕事をしていて厚生年金保険に加入していた場合には、障害厚生年金を受給することができる可能性があります。
3 障害の程度
障害年金を受給するためには、単に自閉スペクトラム症という診断を受けているだけでなく、それによって労働が著しい制限を受ける(3級)、日常生活への適応にあたって援助が必要である(2級)、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とする(1級)と認められる必要があります。
障害厚生年金であれば、3級に認定されれば受給することができますが、初診日に20歳未満の場合や国民年金に加入にしており、障害基礎年金となる場合には、2級以上に該当する必要があります。
障害の状態がこれらの等級に該当するかどうかについては、通常、障害年金を申請する際の医師の診断書が重視されます。
この診断書には、日常生活能力を総合的に5段階で評価する欄と、食事、身の回りの清潔、金銭管理、服薬と通院、対人能力、危機対応、社会性について、それぞれ4段階で評価する欄があり、これらの欄の記載から等級の目安を求めた上で、その他の診断書の記載内容等を総合的に評価して等級を判断することになります。
そのため、自閉スペクトラム症で障害年金を受給するためには、日常生活の状況について、医師に正確な状況等を伝えた上で診断書を作成してもらうことが必要になります。